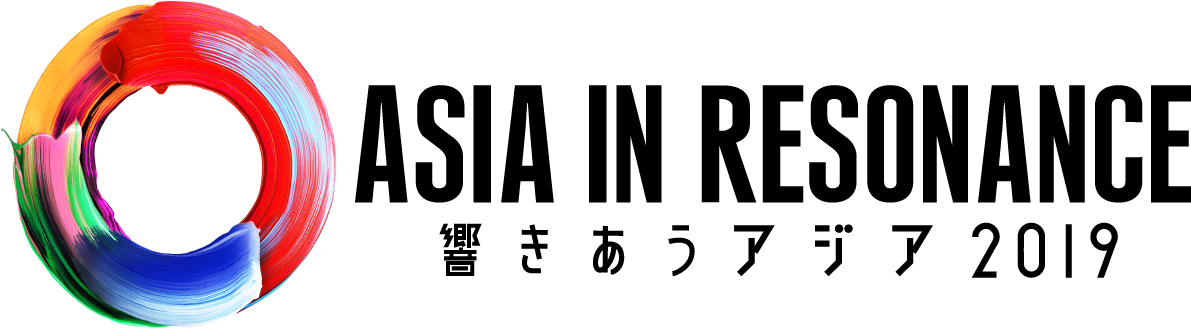『欲望の輪郭』から『プラータナー:憑依のポートレート』へ
原作小説から演劇へ、ともに歩む旅路
2017年末に東南アジア文学賞作家ウティット・ヘーマムーンの長編小説『欲望の輪郭』(小説原題)を読んだことは、とても特別な経験になった。この特徴的な書籍を視覚的に認識することにはじまり、奇妙なタイ文字を使って表紙に印字された作品タイトル、見慣れない判型、紙質と手触り、そして閉じられた本を破り開いて読みはじめなければいけないこと。この小説の物語を受け入れていくうちに、思考と欲望が揺り起こされる。咀嚼できない感情が、幾度も生まれる。読み進めたいと思う一方で、ここで留めておきたいと思う。だが気がつけば、2日で読み終えていた。それからまもなく、この作品が、世界の演劇人から注目される日本のである岡田利規の手によって演劇化されるというニュースを耳にして、いま一度興奮することになった。岡田の著名な作品に、2005年に第49回の岸田國士戯曲賞を受賞した『三月の5日間』がある。小説化されたこの作品は、『わたしの場所の複数』と合わせて小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』として出版され、タイ語にも翻訳された。この小説集は、2008年に大江健三郎賞を受賞した。このレポートでは、2018年7月21日に、The Jam Factory内のCandide Booksで開催された2人のトーク内容を紹介し、2分野の芸術家2人による旅路をたどる。

今回のトークは、ウティット・ヘーマムーンが進行役を務めながら、岡田利規との会話を進めていった。トークの通訳には、タマサート大学講師のティティラット・ティップサムリットクンがついた。トークの冒頭、ウティットが岡田との出会いについて語った。2015年に、ウティットがタイの作家として日本でのセミナーに参加した際に、紹介を受けて岡田と知り合った。その翌年、岡田からの連絡を受けて、2人はバンコクで再会した。その時期に『欲望の輪郭』(小説原題)をちょうど執筆中だったウティットは、小説の物語とアイディアを岡田に語ったのだった。ウティットはこの小説について「とてもとてもエロい本だ」と言いながら、自身の描いた絵を見せてそれを証明してみせた。ウティットの描いた絵画は、小説の主人公である「カオシン」の描いた絵画というアイディアのもとに編纂され、のちに『欲望の下絵』という名の書籍になって出版された。このときの出会いが、この小説を生み出した思想に岡田が大きな興味をもち、コラボレーションの可能性を探る契機となった。岡田は「単にこの小説を演劇として作り変えるだけではなく、継続的な互いの交流と作品の発展を同時におこなうプロセスにする」ことを提案した。ここが、2つの国、2つの文化、2つの芸術分野の境を越えた創作の出発点だった言えるだろう。

2人のアーティストによる交流と協働のプロセスの中で、互いの接続点も見えてきた。それは、2人の育った時代だ。2人とも、1970年代に生まれている。ウティットは言う。「同時代の人々の思想と感情は、接続可能な特性をもっている。だからこそ、岡田がこの結びつきをもとに、小説をどんな形式の演劇に発展させるのか興味深い」。小説の執筆が終わってから、演劇用の脚本作成のプロセスが始まった。異なる言語的な文脈のあいだで、複数回に及ぶ翻訳と推敲のプロセスを経ることになる。岡田は言う。「この小説から演劇を作りたいという直感はとても大事なものだったが、そのあとに必要となったプロセスは大変なものだった」。この言葉は興味深い。その直感とはいったいどんな動機から生まれたのか?この小説とこのコラボレーションのプロセスに対する岡田の視線とは、どのようなものか?そして、どうして演劇でなくてはならないのか?
この小説を演劇に発展させるという関心を岡田に与えたのは、この小説が、身体によって統制され、束縛される人々について語っている点だった。身体の支配下に置かれることは、社会や政府の支配下に置かれることと似ている。彼にとって、このテーマはとても普遍的なものだった。さらに彼は、読者ひとりの個人的な体験である読書行為を、演劇の共通体験に拡張していくことも望んでいた。演劇創作のプロセスに入り、そこに創作チームと俳優が加われば、ふたりの人間のあいだのコミュニケーションだったものが、大きな集団におけるコミュニケーションに変わる。そして最終的には観客が加わって、上演を鑑賞する。ひとつの空間に人々が集まって、その物語を認識し、同時にその物語を経験することは、より拡大された形でその物語に対する視点をもち、それを体験するための、ひとつの可能性になる。とはいえ、舞台化は簡単なことではなかった。原作の小説内には、性的に挑戦的で、過激で、繊細な表現が存在したからだ。さらに、きわめて複雑なタイの現代史の文脈も含まれていた。また、小説という形式から演劇という形式に改変していく中で、異なる条件もある。これらすべてが、脚本・演出として舞台化作品創作を進めていく上での困難となった。

ここで岡田は、『プラータナー:憑依のポートレート』創作プロセスについて語る。彼はタイの現代史への理解を深めるリサーチと情報収集のための時間をとった。さらに、タイの歴史において重要なできごとが起きた場所や、小説内で重要なできごとが起きた場所を訪れ、思想家や学者、歴史的な出来事を実際に体験した人々にインタビューもおこなった。このリサーチによって、彼はタイ現代史の背景や、原作小説を深く理解することができた。他の社会からやってきた人間である彼は、タイ社会のできごとを語ることの難しさを感じていた。歴史的な複雑さや、暴力的な物語のダイナミクス、急速な変化がそこにあるからだ。だが見方を変えれば、タイにおいては、このような変化が他の社会よりもはっきりと見て取れるとも言える。タイ社会がはっきりとしていることで、同様のはっきりとしたダイナミクスをもたない日本社会を顧みることもできる。この発想から、この作品をタイだけではなく、さまざまな場所で上演しようという意気込みが生まれた。彼は、タイの文脈における物語を語り、上演という共通体験を経ることで、さまざまな場所の人々が、自分自身の社会のなりたちや歴史を省察しようという意志をもつことができると思ったのだ。

岡田はつけ加える。フィクションである小説にもとづいて演劇を上演することは、作品そのものにとっても大きな助けとなる。小説の物語を通じて異なる社会の文脈を理解することで、単に情報を得るだけではなく、それらのできごとの影響による情動や感情の状態を知り、もっと深く理解することができるからだ。小説の中でも、登場人物の人生と重なる形で、歴史が語られている。これらの素材を用いてタイの俳優11人との稽古という共同作業に入っていく中で、現代タイ社会の文脈のなりたちやなりゆきがもっと深く理解できるようになるということも分かった。この点について、岡田は小説の演劇化という改変プロセスについて語る。「本当は、小説の物語を舞台上でやってみせるというだけのことを言えば、難しいことではない。ただそれは、面白いとは思わない。演劇というのは、ただ人が物語を読み聞かせて、その様子を視覚的に見せてあげるような感情以上の体験を、観客に与えるべきだからだ」。岡田は、小説とは異なる演劇という形式が表現する力を探求するのに、長い時間を使った。脚本の第1稿で彼は、演劇では使用しないと思われる小説内の場面を試しにカットした。だがその結果として得られた脚本は、小説を読むのと同じような感覚しか与えてくれなかった。それから彼は、切るべきではないシーンを切らないように注意しながら、情報を参照し、創作チームの協力を経て、何度も修正をおこなった。そして第4稿で、稽古に使用する脚本として結晶化させることができた。現在おこなっている俳優たちとの稽古から判断するに、演劇という表現形式によって物語の力を効果的に引き出すことができる脚本になったと思っている。

この演劇作品の上演においてもうひとつ興味深い点がある。それは、ウティット・ヘーマムーンの原作に存在する気違いじみたセクシーさだ。読者にとって、それは欠くことのできない作品の重要な構成要素であり、そこで語られる物語内容に劣らず力をもった、その思想の中心であると言っていいだろう。岡田もまたこう語っている。「演劇という形式には、得意なこともある一方で、あまり得意でないこともある。そのひとつが、セクシーなことを具象的に描写することだ。小説は文章で書かれているのだが、それを読むことで、読んだ人間がいくらでも想像できる。そういった形でセクシーさが伝わる。しかし演劇では、舞台上で役者にセックスしてもらうわけにはいかない。それは観客に対して間違ったコミュニケーションになってしまう。見ている人の想像がそれによってふくらんでいくということは、起こらないことが多い。たとえば、あの役者さんたち舞台上で本当にキスしていてすごいな、とか。観客は目の前の光景に対する考えだけにとらわれてしまい、その状況についての感情にまでコミュニケーションが届かない」。この点に関して岡田は、そのセクシーな状態を演劇において表現するためのアイディアを思いついている。だがそれがどのような形で表現され、どのようなアイディアなのかは、実際の公演に来てほしいとのことだった。ここでウティットが、そういったセクシーなシーンの稽古を見学に行った際の経験を語った。「俳優たちは身体的な言語を用いて、観客を突き放してしまうような猥褻な方向に進むことなく、感情の段階を生み出すことに成功していた。そしてそれが、観客を引きつけて、舞台上に生まれる緊張状態に共感させる美的な力に変わっていた」。岡田は、それが自らの関心であり、実現させたいと思った方針だと指摘した。観客を単なる第三者の立場に置いて、その場のなりゆきを傍観させるのではなく、登場人物と物語にどのように共感させるか、それが演出家としての彼の重要な問題だからだ。「たとえば物語が進んで登場人物が疲れる、そしてその疲れが観客の立場にいる人にも伝わる。こういうことが起きれば、舞台上で起きている登場人物の物語に、観客がなんらかの共感を示しているということが言える。ひとりの人間の人生を本当に知り、理解するというのは、難しく、疲れることだ」。岡田はそう述べる。

筆者はここまでトークを聞いて、文学と演劇のあいだに共通するなんらかの思想というものが、はっきりと分かるようになった気がする。もし原作小説が、読者の個人的な空間における権力の境界線を揺動するものなら、『プラータナー:憑依のポートレート』は、公共空間における社会の一部としての観客の権力の境界線を揺動しているのだ。今回のトークでもうひとつ重要な思想として提示されたのは、岡田の創作と上演における方向性だ。個人としての私たちと、私たちの一部、あるいは私たちとは異なる、他なる物との「境界(Border)」。身体と欲望であろうと、市民と政府であろうと、これらの境界こそ、岡田が上演の方向性の軸として用いたいと望んだものだった。観客と俳優の境界、俳優と登場人物の境界、言語と意味の境界、事実と創作の境界。これらのアイディアは、岡田が上演の方向性を決定するためのリサーチで用いた書籍のうちの一冊である、トンチャイ・ウィニッチャクンの『地図がつくったタイ:国民国家誕生の歴史』から生まれている。これらの境界線を取り除こうとする試みが見せるものは、私たちの身体や主体をさまざまなものと束縛するシステムだ。そこに、社会や政治に対する視点をもつこと以上のところにある、他なる物と結びついた人生の旅のなりゆきが反映される。そして私たちの生き方と、他者、社会、政府、世界との関係についての理想を省察するよう誘う。

今回のトークに参加した筆者は、エドワード・オールビーが1958年に執筆した『動物園物語(原題 ”The Zoo Story”)』のことを思い出した。オールビーが自身の脚本の中で「檻」と呼んでいるものは、筆者の視点で見ると、岡田とウティットが述べた「境界」と比較できるのではないだろうか。60年前の西洋の文脈において、オールビーは、もし人間が社会的規範や規則といった檻から抜け出したときに、人間はまだ生き続けることができるだろうか、という挑戦的な問いを残している。ウティットと岡田のもつさまざまな思想を耳にしたことで、もしさまざまな境界線が壊されて、可視化されたときに、人間はまだ生き続けることができるだろうか、ということに興味をもたなくなった。それよりも興味深いのは、もしそれらの線が可視化されたときに、人間としての私たちの命の定義は、どのように変化するだろうか、ということだ。
ワールドプレミアは、タイ、チュラロンコーン大学文学部ソッサイパントゥムコーモン劇場にて、2018年8月22日から26日の期間に上演される。その後2018年12月に、この作品はフランスのポンピドゥ・センターで上演される予定だ。偶然にも、この作品の主要登場人物「カオシン」も、原作小説内でここの美術館を訪れ、彼が生涯のあいだ敬愛してきた芸術作品を鑑賞する。そして、それらの作品が実際には興味深いものではなかったという事実と直面する。2人の芸術家、2つの文化、2つの芸術分野の境界から、2つの思想、2つの視点の変化というプロセスを経ていく。2つの旅が、私たちの人間としての境界をどのように明らかにするのか。まもなく始まる上演に、その答えを探しにいかなければならない。
文責:タナノップ・カーンチャナウティシット
翻訳:福冨渉