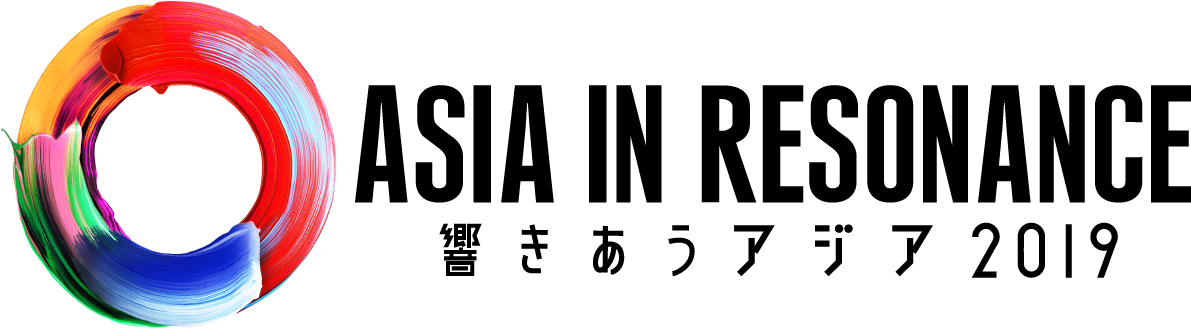ウティット・へーマムーン×岡田利規×塚原悠也のコラボレーションによる斬新さ溢れる大作
2014年の軍事クーデター以降タイで続く政治的混乱の中、精力的に活動を続ける小説家、ウティット・ヘーマムーン。現実/非現実、歴史/神話、政治/個人の間を縦横無尽に飛び回りながら、普遍的な問いに向き合う作品世界が評判となり、東南アジア文学賞やセブン・ブック・アワードを受賞している。『プラータナー:憑依のポートレート』の原作は、へーマムーン自身の半生を色濃く反映した最新長編小説。バンコクに暮らす一人の芸術家が体験したタイにおける政治的動乱と、彼が結ぶ性愛の関係が重ねて語られる。
この小説の舞台化にあたり脚本・演出を手がけたのは、演劇カンパニー「チェルフィッチュ」主宰の岡田利規。若者の日常的所作を捉え、現代演劇に反映する作風で世界の演劇界から注目され、今や日本屈指の演劇作家の一人だ。現代社会に鋭い視座を投げかけてきた岡田がへーマムーンの原作に強く共鳴し、コラボレーションに至る。岡田にとって小説を舞台化するのは初めてで、11名の俳優、4時間の上演など、自身最大規模の作品となった。
空間の演出やデザインを行うセノグラファーとして加わったのがcontact Gonzoの塚原悠也。殴り合いのようにみえるパフォーマンスで国内外に知られ、身体・空間・映像など様々な手法の表現を行う。本作で初めてセノグラフィーを担当し、舞台上の無数の道具や、空間と時間における人物も含めた配置やデザイン、演出に密接に関わる映像の扱いなどを岡田と模索しながら構築。さらに振付も行い、出演もする。ジャンルや手法の境界を越境し解体しながら作品を立ち上げる塚原の真骨頂がこれまでにないスタイルで現れた。
『プラータナー:憑依のポートレート』は、ヘーマムーン、岡田、塚原のそれぞれが自身の立場にとっての新境地に挑み、新たな芸術性を獲得した点においても極めて斬新な作品なのである。
多彩なタイ人のキャストとエマージングなクリエイター陣により展開する上演
バンコクでのオーディションで選ばれた11人の俳優の役柄は固定されず、俳優、観客、ナレーターとなり、舞台上と観客席に語りかける独特の作品構造を見事に体現する。年齢もキャリアも多岐にわたり、演劇だけでなく、音楽や映画など多様な領域のアンサンブルが実現した。
クリエイティブチームを成すのは、タイと日本の新進気鋭のクリエイターたち。演出助手はヨーロッパで最も注目されるフェスティバルであるブリュッセルのクンステンフェスティバルデザールやウィーン芸術週間にて2019年に招聘が決定している演出家、ウィチャヤ・アータマート。衣裳は劇団「快快」メンバーとしての活動の他、国内外の演劇、ダンス、美術、音楽家の舞台衣裳を独自の感性で手がけ、近年の岡田利規作品に多く携わる衣裳家、藤谷香子。照明デザインは、アピチャッポン・ウィーラセクタン『フィーバー・ルーム』の照明デザインを担当し、舞台照明の概念を覆す実験的視点を持つポーンパン・アーラヤウィーラシット。音響デザインはサウンドアーティストとしてインスタレーションやパフォーマンスの作品も発表する荒木優光。映像はcontact Gonzoで塚原と共に活動し、グラフィックデザイナーや写真家としての顔も持つ松見拓也。
本作は、俳優はもちろん、今後の演劇界の担い手となるに違いないクリエイター陣ひとりひとりが、上演コンセプトに密接に関わり互いに交錯しながら、展開される。
アジアにおける芸術家と芸術史にみるジェンダー、階級、世代、政治、芸術の境界線とは
『プラータナー:憑依のポートレート』は、タイに生きる一人の芸術家の人生を描きながら、人生を取り巻く社会状況や、「生」の普遍的な問いを突きつける。自己/他者、生/死、男/女、ある階級/別の階級、過去/未来、個人/国家、西洋芸術/その周縁の芸術史、支配する側/支配される側、欲望/その対象——現代社会を生きる上で誰もが対峙する見えざる境界線が、本作のテーマのひとつである。生きる上で葛藤の原因ともなるあらゆる境界線は、岡田と塚原が編み出す手法で、舞台/客席、現実/虚構とも混ざり合い、その場にいる者すべての体験として現れる。境界線は越えられるものなのか。それとも越えられずに存在し続けるものなのか。幾度も立ち現れる「境界線」を、どうか捉えていただきたい。
演劇における「フィクション」の新たな形態
劇中劇のスタイルで展開される本作では、11名の俳優が、ある時は主人公を、ある時は主人公に関わる人物を、ある時は誰でもないナレーターを演じる。俳優たちは、休憩を挟み4時間にわたる上演を通じて舞台上に存在し、時には舞台上における「観客」としても存在。舞台上の俳優と観客席の観客との間の一方通行ではない、いくつもの関係性に重ねられる「語り」の構造を立ち上げていく。
舞台に登場するのは、俳優だけではない。通常の舞台作品では裏に控えていることの多いクリエイティブチームが、セノグラフィーの塚原悠也を中心に常に舞台上に存在。シーンの一部として登場したり、装置や道具の移動を俳優と共に行い空間を変化させたりしながら、劇中劇の構造をより際立たせる。舞台上で繰り広げられる物語は、新たな「フィクション」の形態として生まれ、塚原をはじめ「出演者」ともなるクリエイティブチームの存在は、その骨組みを見せる役割を果たしている。
交錯する複数の関係性と幾重の構造により生み出され、その瞬間をも露わにする本作は、観客の「鑑賞する側」としての態度を揺るがす。4時間の上演後、この「物語」を引き継ぐのは、「見ている」はずであった観客なのだ。
「見つめる人間と、見つめられる人間」
舞台上の物語を鑑賞することに留まらない、演劇という表現形式における新規の鑑賞体験が得られるに違いない。